|
���J���^���N�̏d�v����i����B
|
�l���Ă݂�Ɨ��ߒr�������n��ł͐̂�������Ă����͂����B
�W���s�����������邽�߂ɂ́A���ߒr������Ȃ��n��ւ̋�̓I���s�������d�v�ł���Ǝ��B�͍l���Ă���B
�ȉ��A�J���^���N�̎��p���𒆐S�ɋL�q����B
|
| �^���N�̃^�C�v�Ǝg�p�G���A |
|
�������͉J�����p�̃Z�O�����g�����̎l�����ōl���Ă��܂��B�Z�O�����g�̗v�f��2�B�u�ݒu���@�ɂ��^���N�̃^�C�v�v�Ɓu�����C�O�Ƃ����g�p�G���A�v�ł��B
| �@�@ |
���@�� |
�C�@�O |
| ���������^ |
�J�����o�}���E�ЊQ�Ή�
�i�s�s�������j |
�J�����o�}���E�ЊQ�Ή�
�i��i�n��j |
| �P�ƏW�������^ |
�ЊQ�E�_�ƐU���Ή�
�i���ׁE�R�ԕ������j |
�J���E�Y�ƐU���Ή�
�i���W�r��n��j |
���̎l�����ɂ킯�āA���ꂼ��̎��_�őΉ���i�߂�B
�i�ȉ��̃C���X�g�͈ꋉ���z�m�ł���J�����p�̐��Ƃł��鍕��N�F���쐬�����ݒu�C���[�W�ł��B�j
|
| �^���N�^�C�v�P�F���������^ |
|
�������̉������Ŏ~�߂��J�����p�C�v���ŏW�߂Đݒu�����^���N�Œ�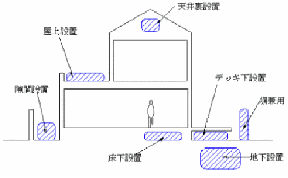 ���A���p����B ���A���p����B
�������̌`��ɍ��킹�ėl�X�g�ݍ��킹�邱�Ƃ��\�B
�������ɕ��݂��邱�ƂŐݒu�R�X�g���}���邱�Ƃ��ł��A�^���N�̈ێ������e�i���X���e�ՂɂȂ�B
�������ɕ��݂��邽�ߐݒu�X�y�[�X�̊m�ۂ���r�I�e�Ղł���A�l�̏Z����������{�݂܂ŕ��L�����p�`�Ԃ������܂��B
�܂���L�����v�⌻�n�A���������̐ݒu�Ɠ�����Ƃ̒��ŒZ���ԂŔ����t���邱�Ƃ��ł���B
 100���b�g�����x���琔10�g���A��100�g���܂ʼn\�B 100���b�g�����x���琔10�g���A��100�g���܂ʼn\�B
�E�̎ʐ^�͉������Ƀ^���N�����߂�H���r���̂��̂ł��B
|
| �^���N�^�C�v�Q�F�P�ƏW�������^ |
|
�P�ƏW�������^�^���N�̃����b�g�͂Ȃ�ƌ����Ă��ꏊ��I�Ȃ����Ƃł���B
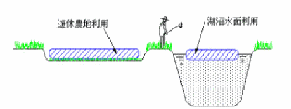 �������̑S���Ȃ��r�n�ł��A�X�̌�������R�ł��A�ЊQ����̏Ă��쌴�ł��A�y�n�̋����C�ӂ̓y�n�ł��A�C��ł��A���������͐�̏�ł��A�^���N��ݒu���邱�ƂŒW���ł���J���ڒ����A���p���邱�Ƃ��ł���B �������̑S���Ȃ��r�n�ł��A�X�̌�������R�ł��A�ЊQ����̏Ă��쌴�ł��A�y�n�̋����C�ӂ̓y�n�ł��A�C��ł��A���������͐�̏�ł��A�^���N��ݒu���邱�ƂŒW���ł���J���ڒ����A���p���邱�Ƃ��ł���B
�z�Ǔ��̐ݔ��H�����ŏ����ő傫�Ȍ��ʂ��Z���ԂŊ��҂ł���B
�܂��g�p�f�ނ����O�����ɂ������\���ƂȂ��Ă���ϋv���ɂ��D��Ă���B
�T�C�Y��100���b�g�����x���琔10�g���A�A�����邱�ƂŐ�100�g���܂ʼn\�B
�i�����o�蒆�j
|
| �g�p�G���A�P�F���� |
|
�s�s���ɂ����Ă͈������Ȃǐ������ւ̐ؔ�������@���͂قƂ�ǂȂ��̂������ł͂Ȃ����B
�����ǂ��Ƃ����킯�ł͂Ȃ����A�s�s���Z���ւ̑i���́u���o�}���v�Ɓu�ЊQ�v��ł���B
�u���o�}���v�Ƃ́A���K�͈ȏ�̓y�n�����ɍ~��J�������̂܂܉������ɔr�o����ƍЊQ�̌����Ƃ��Ȃ邽�߁A�ꎞ�I�ɒ������邱�ƂōЊQ�̔�Q���������Ƃǂ߂悤�Ƃ������z�Ɋ�Â����̂ł���B
���y��ʏȂ͗��撙���Z�����Ƃ̈�Ƃ��āA�J�����p���o�}���Ɋ֘A����Ő��[�u��݂��Ă���B
�e�����̂ł͂������`�ŁA�~�J�ɂ�鐅�Q�̖h�~�A�y���Ȃ�тɓs�s���̌����}�邽�߁A���ʐρi�T��500�u�Ƃ��Ă���P�[�X�������j�ȏ�̕~�n�Ɍ��z�������݂����Ƃ��ɁA�Z�����E�Z���n�����ǁE�������ܑ��E�����{�ݓ��̉J�����o�}���ݒu�𐄐i���Ă���B
�Ⴆ�A�w�Z�Z�ɂ��^�����{�݂����L����n�������́A�{�Ѓr�����^�H��A�����Z���^�[�����L�Ǘ������ƂȂǂ͂����������������l��������g�݂̏d�v�����[���ɔF�����Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B
���̓s�s���ЊQ�̖h�~����̗L���Ȏ�i�Ƃ��ĉJ���^���N������B
���ׁE�R�ԕ��ɂ����ẮA�ЊQ��Ƃ��킹�Ė����I�Ȑ��s���������������Ƃ��Ĉʒu�Â��邱�Ƃ��ł���B
�����ɂ����Ă��A�R�ԕ��Ⓡ�ׂɂ����ẮA�[���Ȑ������m�ۂ��邱�Ƃ�����Ȓn�悪��������B
�n���I�ɌX������Ȃǂ̗��R�ʼnJ���̒������ł��Ȃ������n��ł́A�J���^���N�̐ݒu�ŁA�k��p�A�����p�ɗ��p���邱�Ƃ��ł���B
�܂��w�Z�{�݂Ȃǔ��w��ꏊ�ɐݒu���邱�ƂōЊQ���̈������̊m�ۂ��ł���B
|
| �g�p�G���A�Q�F�C�O |
|
���{�����ł��������̊m�ۂ�����Ȓn�悪���邪�A�C�O�͂���ȏ�Ɍ������ł���B
���łɌ������������Ă���ꏊ�ɒZ���ԂŌ������ɉJ���^���N�݂���ƂƂ��ɁA���J���n��ɂ͒P�ƏW�������^�^���N��ݒu���Ă��������B
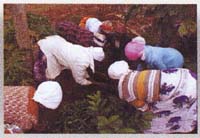 �u����������앨�����邱�Ƃ��ł���B�v �u����������앨�����邱�Ƃ��ł���B�v
����Ȓn�悪���W�r��n��ɂ͂�������B
�J���_�@�ɂ���čĐ������C���h�E�j�[�~�����������B
���̍ŏ��͉J���𗭂߂�r�����邱�Ƃ������B
�A���ɂ���ĐX�̐N�H��h���A�ѐ��͂������y�n�ō앨�����n�߂��P�j�A�n�悪����B
��]���琶�����]�ւ̓]�����ʂ������A���̓]�@�͂킸���Ȑ��ƈ�l�̐l�Ԃ̍s���������B
�����������K���ׂ����P���A�����ɂ���B
���B�ɋ��߂��Ă��邱�ƁB����́A���ł��邱�Ƃ���n�߂邱�Ƃ��B
|